気温が急に上がった朝、窓を開けた瞬間に、やわらかい風が部屋に入り込んだ。湿り気を含んだその空気は、どこか土の匂いと若葉の匂いが混じっている。寝ぼけた目が一瞬で覚めるわけでもない。けれど、鼻先をくすぐるその匂いが、春の訪れを静かに告げていた。
毎年この季節になると、決まって胸の奥がざわつく。声にならない感情が、深いところからゆっくりと浮かび上がってくる。名前をつけるには漠然としすぎているけれど、ひとことで言えばそれは「始まり」だ。何かが、あるいは何かだったものが、また別のかたちで始まる予感。その気配に触れただけで、理由もなく立ち止まりたくなる。
春はなぜこんなにも希望のかたまりなのか。街を歩けば、新しい制服に身を包んだ学生、ぎこちなく歩く新社会人、久しぶりに再会したような木々の新芽が、等しく「これから」を身にまとっている。出会いや別れのドラマを引きずるようにして、誰もが季節のなかを歩いている。その空気を吸い込むと、不思議と自分も「何かを変えたい」と思ってしまう。大きな決意じゃなくていい。ただ、もう少しだけ背筋を伸ばして歩きたい。そんなささやかな意欲が、胸の内で芽吹く。
春は、夏の入口にある季節。真夏の眩しさとは違い、まだ躊躇いや静けさを含んでいる。けれど、その内側では、確かに何かが動き始めている。日ごとに陽射しは力を増し、空の色も少しずつ変わる。木々の緑が濃くなるたび、自分の中にも目覚めの合図が響いてくる。うまく言葉にできない感情が、風に背中を押されて少しずつ前に進んでいく。
この季節になると、昔のことをよく思い出す。別れ際に交わした短い会話、黙って見送った背中、もう二度と戻らない時間。なぜか、春になるとそれらがひとつずつ浮かび上がってくる。まるで空気のなかに記憶の粒が混じっていて、それが心のどこかに触れてしまうのかもしれない。通い慣れた道、見慣れた景色が、春の匂いとともに、過去の情景を呼び起こす。
春は、やさしい顔だけをしていない。新しい門出を祝う花の下で、自分だけが立ち止まっているような感覚に陥ることもある。誰もが未来に向かって歩いていくなか、自分はこのままでいいのかと問われるような瞬間がある。桜が咲き誇る景色の中で、かえって孤独が際立つことがある。春の光は柔らかい分だけ、影もまた深く見える。
それでも春は、希望を手放さない。決して派手ではないが、確かにそこにある余白。何かが変わるかもしれないという、かすかな期待。その余白があるだけで、人は前に進める。春がもたらすのは、そんな小さな勇気だ。何かを始めたくなる衝動が、いつしか行動に変わる瞬間。そのきっかけは、たいてい春の匂いとともにやってくる。
春の陽射しは、まだ少し頼りない。風もときどき冷たく、朝と夜の気温差が体に残る。けれど、その不安定さこそが春の本質かもしれない。一気に変わるのではなく、少しずつ、でも確実に、景色が変わっていく。その“少しずつ”のリズムに心を合わせながら、自分もまた変わっていく。
道端の花が咲きはじめ、スーパーには春野菜が並ぶ。電車のホームには、新しい通学カバンを持った子どもたちがいて、陽に透ける制服が新鮮に映る。そうした日常のひとコマが、春の訪れを教えてくれる。それに気づけた自分が、どこか誇らしく、少しだけ安心する。
大きな変化を起こさなくてもいい。朝にお気に入りの音楽をかける、少しだけ部屋を片づける、それだけで気持ちは変わる。春は、そういう“ほんの少し”を受け入れてくれる。大きな夢じゃなくていい。ただ、今日をちゃんと過ごす。その積み重ねを、春はそっと肯定してくれる。
だから、春のざわめきには耳をすませていたい。胸の奥で鳴る小さな音、不安と期待の混ざった感情。それらすべてを抱えて、この季節を歩いていく。春は、そうやって“何かになろうとする途中”の自分に、いちばん寄り添ってくれる季節なのだと思う。
たっくす
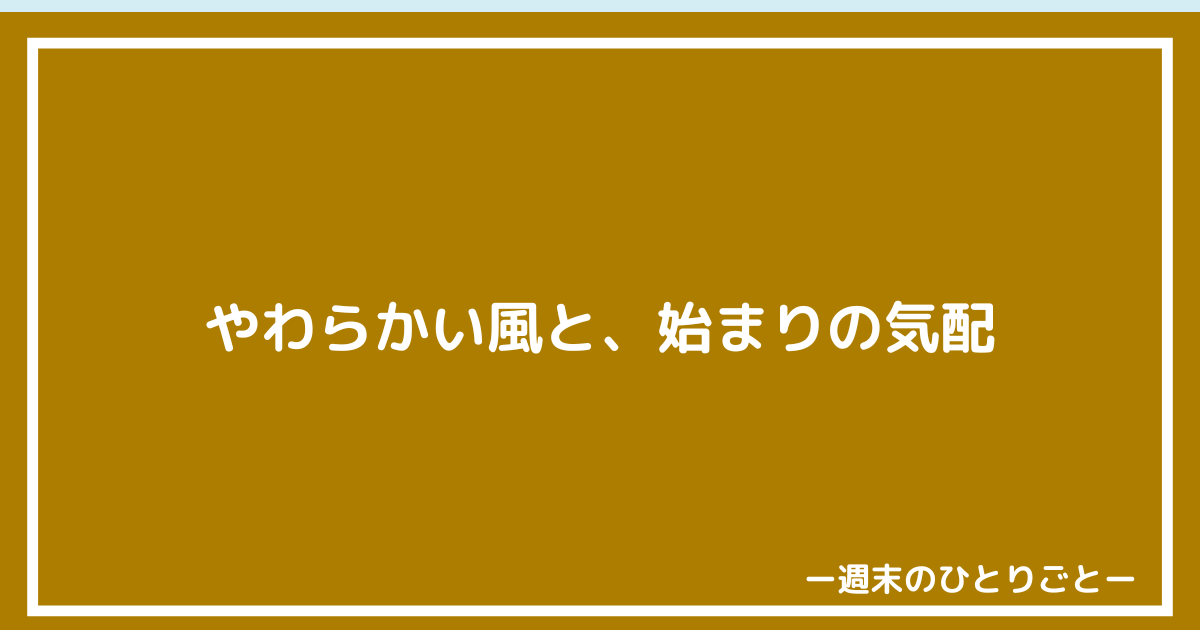
コメント