会計の世界には、「費用収益対応の原則」という考え方があるらしい。収益が計上されるならば、それに直接結びつく費用も同時に認識しなければならないという原則。売上だけをひとり歩きさせることは許されず、それを生み出すために払った代償もまた、等しく帳簿に刻まれる。ごまかしのきかない、冷静で整った世界のルール。
この原則を初めて耳にしたとき、ふと別の光景が浮かんだ。会計とは無縁の、もっと曖昧で不確かな日常の中で、僕たちが何かを「得よう」とするときの姿勢だ。
人は何かを欲するとき、手に入れ方ばかりを考える。どうすれば取れるか、どうすれば勝てるか、どうすれば掴めるか。欲望が先に立ち、それに続くのは戦略や計画だ。たとえば資格試験を目指す者なら、どの参考書を使うか、どの講座が効率的か、何時間勉強するべきか、そんなことばかりを考える。ところが、その「得る」という行為には、必ず何かを失うという側面がある。その失い方について、ほとんどの人は無自覚だ。
時間、体力、気力、人間関係。ひとつを選ぶということは、他のいくつかを選ばないということに他ならない。けれど現代の生活は、多くを並行して進めることを美徳のように語る。仕事も、家庭も、趣味も、成長も、全部同時に抱え込み、全部をうまくやり切れる人間こそが「できる人」だとされる。
その幻想に従って、手放すことなく、得ることばかりを繰り返していく。結果、頭も心もスケジュール帳も、キャパシティを越えてパンパンになる。あらゆる「費用」は気づかぬままに積み重なり、やがて「破綻」というかたちで現れる。
会計の世界なら、収益に対して費用が対応していないと「おかしい」と即座に判断される。けれど僕たちの心の中では、そのズレに気づくセンサーが鈍くなっている。収益だけを求め続けて、費用を棚上げにしてしまっている。その姿はどこかで、「失うこと」にきちんと向き合っていない自分の在り方と重なる。
本当は、何かを得たいならば、まずその対価として何を差し出すかを考えるべきなのだ。時間を使うのか、余暇を諦めるのか、友人との時間を減らすのか、それとも安心感や惰性を手放すのか。その失うものが、自分にとってどれほど大きいのか、耐えられるのかを見極めなければ、得るべきものへの道筋も定まらない。
だからこそ、「どう得るか」だけでなく、「何を失うか」にも意識を向けること。それが、自分のキャパシティを守るための唯一の方法だ。
結局のところ、人生もまた、帳簿のようなものかもしれない。収益を得るには、それに見合う費用がかかる。その帳尻を自分で合わせ続けていかなければならない。そうしなければ、気づかぬうちに赤字を抱えて、心のどこかで破産してしまう。
何を得るか。それと同じくらい、何を失うか。それを選ぶことが、生きるということの本質なのかもしれない。
たっくす
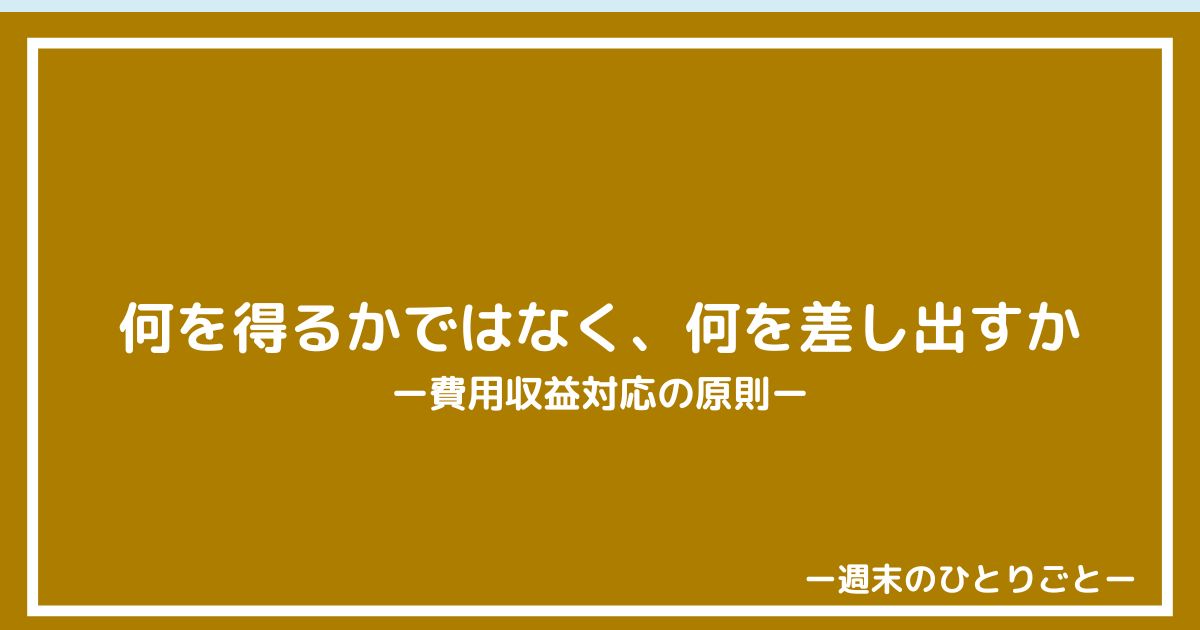
コメント