社会に出てから、まだ10年は経っていない。けれど、指の間をするりと抜けていくようにして、気づけば10年が目前にある。目の前にある日々をひとつずつ噛み砕いてきたつもりなのに、振り返れば足跡は思いのほか遠くまで伸びている。
この10年弱で痛感したのは、「言語化」の力だ。仕事を進める上で、何をどう思っているのか、どんな課題があるのか、どうしてそう判断したのかを、正確に、過不足なく伝える必要がある。感覚のままに放っておけば、解像度の低い表現がそのまま誤解を招き、些細なズレが後々のトラブルを呼ぶ。ネクストアクションが曖昧になり、手戻りが発生し、結果として余計な疲弊が生まれる。そんなことは今や当たり前の知見として、多くのビジネス書や動画コンテンツが口を揃えて語っている。
ただ、それでもなお、僕の中には「言語化できない感情」を大切にしたい自分がいる。
たとえば「なんでか分からないけど好き」。理由がわからないけれど心が動く、そういう感情。理屈じゃなく、言葉でもないところで揺れ動く琴線。それを無理やり言葉にしてしまうことで、何かがこぼれ落ちてしまう気がする。言葉にしてしまった瞬間に、それは言葉の範囲に閉じ込められてしまうから。だから僕は、そういった感情はブラックボックスのままでいいと思っている。触れられないものとして、そっとしておきたい。大切に箱に仕舞っておくように。
理由はない。あえて言うなら、「理由を探そうとすること」そのものが、言語化のファーストステップになってしまうから。わからないままにしておきたい。言葉にならない感情があることを、ただ静かに肯定していたい。
小説が好きだ。とりわけ、読後に心の奥がふるふると揺さぶられるような作品に出会うとき、その揺れは圧倒的で、美しくて、何より抗いがたい。最終ページを閉じた瞬間、誰かに話したくなる。でも、それがなぜなのかを問われると、一気に言葉に詰まる。どのシーンで、どの台詞で、どんな構成で——そういった分析を始めた時点で、もうその感情には届かなくなってしまう。だから、あの「揺さぶられた理由」を考えるのは、どこか野暮に思えてしまう。
社会人として成長する中で、僕は間違いなく多くのことを言語化できるようになった。課題と対策を切り分け、事象を構造化し、論理の積み木を高く積み上げる。曖昧な感覚を言葉に変え、他者と共有し、意思決定の速度を上げる。成長とはそういうものなのだと思う。そうでなければ、仕事は回らないし、誰とも歩幅を合わせられない。
ただ、その「成長」が進めば進むほど、「言語化したくない自分」が、少しずつ弱くなっていくのを感じる。まるで砂が水に溶けていくように、ふわりとした感情をふわりとしたまま抱えていることが、難しくなっているのだ。
それでも僕は、言葉にできないものを手放したくはない。たとえその感情が誰にも伝わらなくても、論理的でなくても、説明できなくても、そこに確かに在るということを信じていたい。
平日は、言語化に勤しむ。定時のチャイムが鳴るまで、ロジックを磨き、言葉を研ぎ澄まし、曖昧さを切り捨てながら進む。そうしなければ、仕事にはならない。
けれど休日になると、僕は小説を開く。誰かの言葉で編まれた物語に身を投げ出し、そこにある言葉にならない感情に触れる。理由なんて要らない。ただ、「なんでか分からないけど揺さぶられる」その瞬間に、自分の輪郭がもう一度浮かび上がる気がする。
だから、言葉にできない感情を捨てるつもりはないし、捨てたくもない。言語化できる力と、できないものをそのままにしておける力。その両方を持ち続けたい。言葉の外にあるものを見失わないように。
心が揺さぶられたとき、僕はいつも黙っていたいと思う。
たっくす
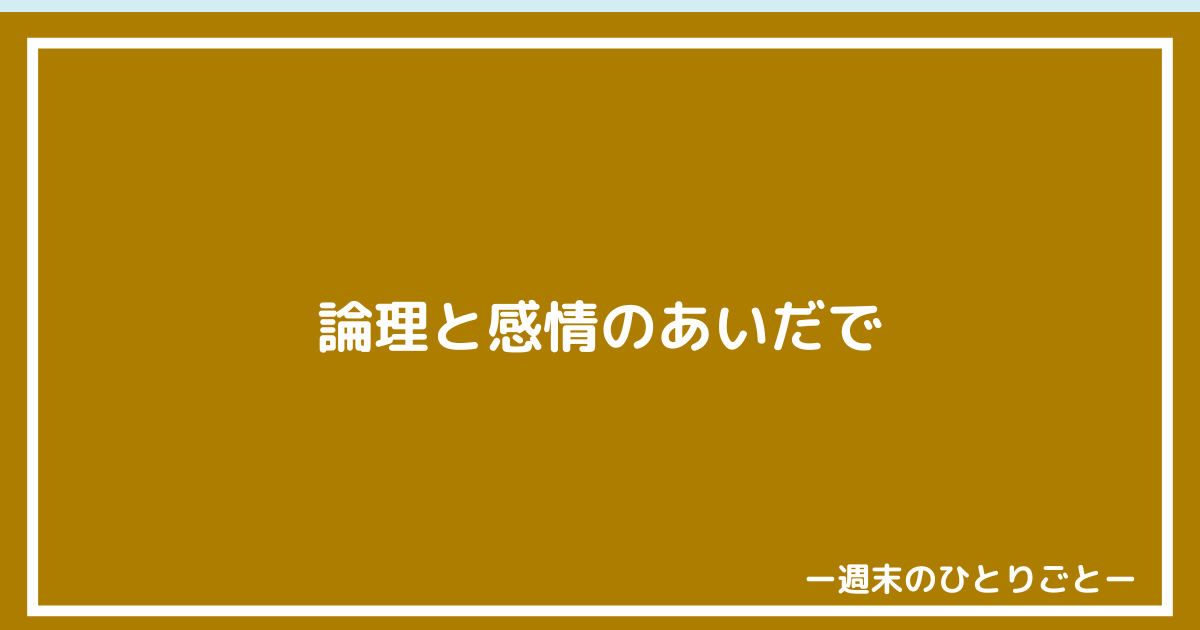
コメント