ポケットに滑り込むその薄く冷たい板は、世界そのものを圧縮した装置である。触れるだけで扉が開き、言葉が溢れ、映像が流れ、世界の鼓動が手のひらに響く。かつて、遠く離れた人との会話には時差と不便が付きまとい、情報に辿り着くには足と時間を要した。今は違う。スマートフォンという魔法の装置が、距離という概念をもはや無効化した。人々は国境を越えて交わり、思想は瞬時に伝播し、知識は求めるより先に提示される。世界は常に接続されている。常に動いている。そしてその動きは、日々の暮らしに無意識のうちに染み込んでいる。
駅のホーム。夕暮れの電車内。カフェの窓際。街に生きる人々の多くが、掌の中の光に視線を注いでいる。無言のまま、指先だけが律動する。声なき会話、音なき旅、目の前ではない「どこか」と常に接続されたまま、日々は流れていく。
そこにあるのは利便と快適、そして無数の選択肢。何かを知りたいと思えば、検索窓に文字を打ち込むだけで答えが返ってくる。数え切れないほどの動画、音楽、ニュース、論文、娯楽。すべてが即時的に手に入る。もう新聞を開く必要も、リモコンを探す必要もない。リビングに腰を下ろす必要すらない。ベッドの中でも、バス停でも、満員電車の中でも、知りたいこと、見たいもの、聞きたいことがすぐそこにある。
だがその光は、時に視野を狭め、思考を奪う。情報の奔流に身を浸しすぎたとき、人は自らの「問い」を失う。自分で選ぶという行為が、他者によって最適化された「提案」にすり替わる。アルゴリズムが導くままにスクロールし、タップし、次のコンテンツへと誘われていく。自分で選んでいるようで、実は選ばされているのではないか。自分の興味すら、誰かによって形作られているのではないか。
情報は知識に変わる。しかし、受け取るだけでは知恵にはならない。そこに「選ぶ」という行為が必要だ。何を知るかではなく、何を知らないままでいるか。何を見るかではなく、何を見落とすか。それは誰かに委ねることのできない、きわめて個的な判断だ。
スマートフォンは世界との接続点でありながら、同時に現実との断絶点にもなりうる。空を見上げること。風を感じること。人の表情を読み取ること。そんなささやかな瞬間が、画面の向こう側にかき消されていく。列車の窓に流れる景色がどれほど美しくても、それに気づく者は少ない。なぜなら、その視線は小さな画面に吸い寄せられているからだ。
たった一度、ポケットにその装置をしまうだけで、世界は静かに姿を変える。風がどこから吹いてきたかに気づく。木々のざわめきが、ひとつひとつ異なる音を奏でていることに気づく。隣に立つ人のかすかな表情の変化が、何かを語りかけていることに気づく。そうした「気づき」は、情報ではない。それは、生であり、実感であり、存在の輪郭そのものだ。
便利であること。それ自体は悪ではない。技術の進歩は人類の叡智であり、未来への扉でもある。だが、その扉を開けるのは自分自身であるべきだ。開けっぱなしにされた扉の向こうにあるのは、果たして本当に望んでいた光景なのか。問うことをやめた瞬間、我々は「選択する存在」ではなくなる。
スマートフォンとともに生きるこの時代。だからこそ、自分の眼で見る、自分の耳で聞く、自分の心で感じるという原点に立ち返る必要がある。情報社会のなかで溺れるのではなく、泳ぎ切る力を持つこと。そのためには、時に立ち止まり、装置から目を離し、世界そのものを見つめ直さなければならない。
選ぶこと。問い続けること。見落とさないこと。それが、スマートフォンという便利すぎる装置との共存において、最後に残された「人間らしさ」なのかもしれない。
たっくす
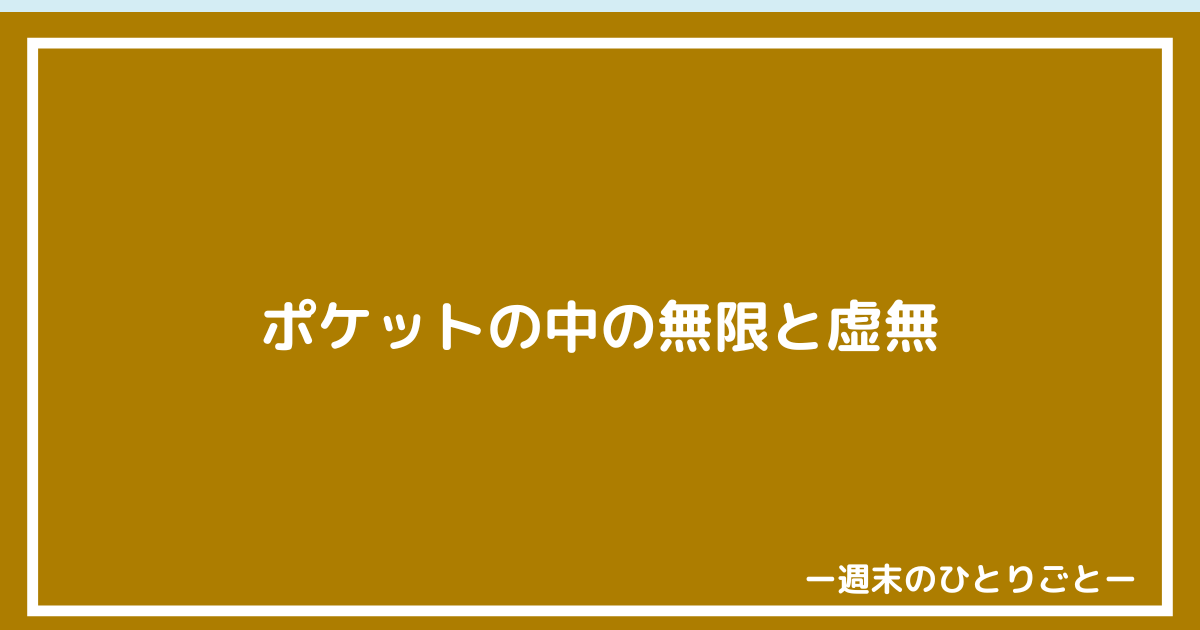
コメント