AIは素晴らしい。
仕事においても、プライベートにおいても、もはやAIを使わない日はない。朝、目覚めとともにスマートフォンを手に取り、ニュースをチェックすれば、そこにはAIが選別した記事が並ぶ。メールやチャットの文章を考える際、AIの補助を借りることも増えた。企画のアイデアを練るとき、一人で考えを巡らせるよりも、AIに問いかけて壁打ち相手にするほうが、ずっと効率的に思考を深められる。
それはもはや、呼吸のようなものだ。意識せずともAIが身近に存在し、生活や仕事を滑らかにする。AIは補助輪のような役割を果たし、僕たちの思考や行動を支えてくれる。けれど、時折ふと思うことがある。
もし、これがもっと高度になり、誰しもが当たり前のようにAIを活用するようになった世界では、人と人のやりとりはどのように変わるのだろうか。もしかすると、すべての対話の間にはAIが介在することになるのではないか。
「何かを伝えたい」と思った瞬間に、直接相手に言葉を紡ぐのではなく、AIが最適な表現を考え、相手に届ける。相手はそれを受け取り、自分で返答を考えるのではなく、またAIを通して返事をする。そんな未来は、果たして豊かなのか。
「ありがとう」や「ごめんなさい」さえも、AIが適切な言葉を選び、僕たちの代わりに伝える世界。人と人とが本来交わすべき感情の揺らぎや、言葉の温度は、どこに行くのだろう。効率的で、誤解もなく、洗練されたコミュニケーションが成立するかもしれない。でも、それは果たして本当の意味での対話と呼べるのだろうか。
対話には、言葉以上のものがある。間の取り方、言葉に詰まる一瞬、表情のわずかな変化。そうしたものがすべて洗練された合理性の裏に消え去る時代が来たとしたら、それは幸せなのか。それとも、寂しさを伴うものなのか。
AIは、決して冷たい存在ではない。適切な言葉を提示し、感情を理解しようとする。だが、そこに宿るのは「擬似的な感情」に過ぎない。人間が持つ曖昧さや、誤解や、未熟さがあるからこそ生まれる「余白」のようなものは、AIが仲介することで失われてしまうかもしれない。
言葉は、伝えるものではなく、通じ合うものだ。誰かと話すとき、僕たちは単に情報を交換しているわけではない。そこに宿る気持ちや、言葉の裏にある微細な温もりこそが、人と人とを繋げている。AIがその橋渡しをすることで、円滑な会話は生まれるかもしれないが、本当の意味での心の交流は、次第に希薄になっていくのかもしれない。
それでも、僕はAIを使う。仕事をする上で、AIの助けが必要な場面は多い。アイデアを整理するために、文章をより洗練させるために、そして時には思考の壁を超えるために。AIなしには、もはや成り立たない仕事も増えている。
ただ、ふと手を止めたとき、考える。僕たちはいつまで、人と人とが直接対話する世界を保てるのだろうか。どこまでが便利で、どこからが喪失なのか。その境界線は、僕たちが思うよりも、ずっと曖昧なものなのかもしれない。
言葉がAIのものではなく、僕たち自身のものとして残り続けるために、僕たちはどうするべきなのか。その答えを見つけるのは、今ではなく、これからの僕たちの在り方にかかっているのだろう。
たっくす
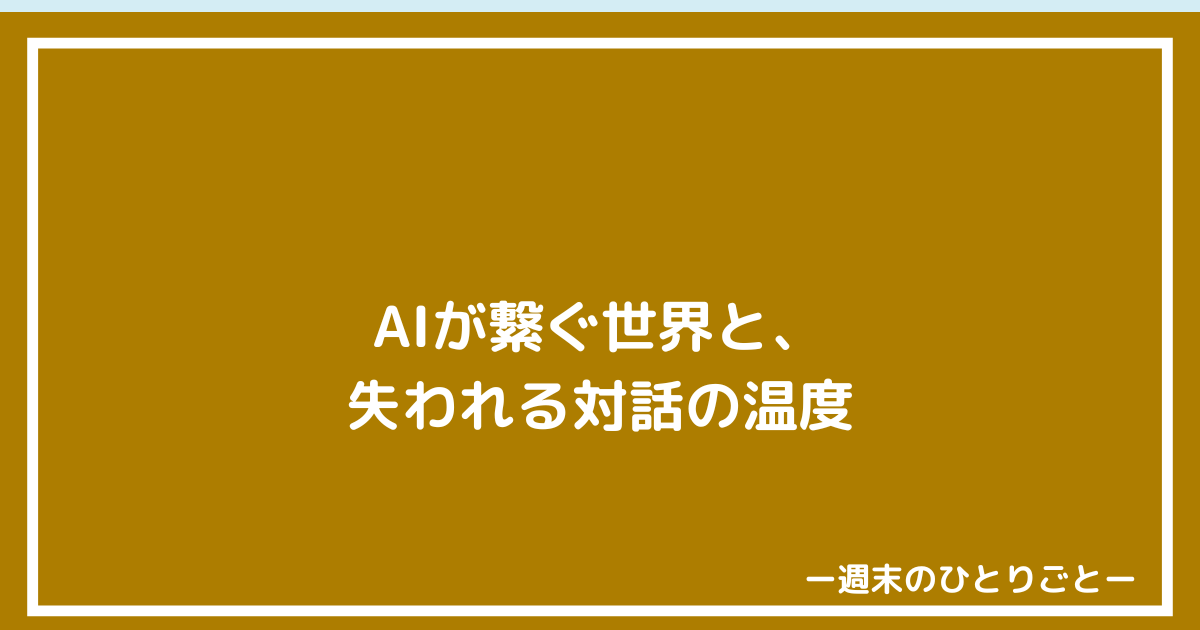
コメント