かつて、夢の国と呼ばれたその場所には、まだ夢が残っていた。
約10年ぶりにディズニーランドを訪れた。季節は春。花々が咲き乱れ、空はやわらかく澄んでいた。ゲートの向こうに広がる光景は、一見するとかつてのままだった。ミッキーの耳をつけた子どもたちの笑い声、甘いポップコーンの匂い、遠くから聞こえるパレードの音楽。すべてが懐かしさを含んで胸に迫ってきた。けれどその実、あらゆるものが変わっていた。
十年という歳月は、何かを確かに変えてしまう。
園内には新しいアトラクションがいくつも増えていた。料金は以前より高く、ファストパスという名の紙片も姿を消していた。システムは洗練され、予約も入園もスマートフォン一つですべてが完結する。整えられた合理性の中に、戸惑いにも似た感情が生まれた。
昔は、紙のマップを手にすることからすべてが始まった。入り口近くのスタンドで配られる色とりどりの地図は、まるで宝の地図のように感じられた。ページを広げ、どこから回ろうかと友人たちと頭を寄せ合って話し合った。紙はすぐに折り目だらけになり、ポケットの中で曲がり、角が破れた。歩くごとに汗や雨でくたびれていくそのマップに、確かにその日の軌跡が刻まれていた。
しかし今では、マップはスマホの画面に収まっている。現在地も、アトラクションの場所も、待ち時間までもが一目でわかる。迷うことはない。戸惑うこともない。すべては指先ひとつで手に入る。情報も、予約も、楽しみ方さえも。無駄がなく、隙もない。完璧な「楽しみ」が、あらかじめ用意されていた。
スマホを開いた瞬間、ふとした違和感が胸をよぎった。地図や待ち時間の隣に、SNSのアイコンやメッセージアプリの通知が並んでいる。日常の中で見慣れたそれらのアイコンが、夢の国の風景の上に重なっていた。現実の断片が非現実の中に滑り込んでいる。たったひとつの画面の中で、夢と現実が混ざり合う。その混濁が、何か大切な境界を曖昧にしてしまったように思えた。
昔はそうではなかった。スマホは今ほど万能ではなく、夢の国に足を踏み入れた瞬間、現実は外に置いてくることができた。通知に邪魔されることもなく、地図や待ち時間に気を取られながらも、視界に映るものはすべてディズニーランドの一部だった。そこには確かに「切り替え」が存在していた。現実の影が、非現実に介在することはなかった。
それでも、違和感があった。きらびやかな風景の中で、ふと心に空白が生まれた。紙のマップを探す癖は、まだ身体に染みついていた。ふと目線を上げ、遠くにある待ち時間ボードを探す瞬間もあった。しかしもう、それらは必要のない行為だった。すべてが簡潔に、明快に、そして即座に提供されていた。
便利であることは、間違いなく良いことだ。時間を無駄にせず、スムーズに目的地へたどり着く。けれど、そこに余白はなかった。予想外の出会いも、偶然の驚きも、あらかじめ用意された選択肢の外には存在しない。もしかすると、夢の国から「夢」と呼ばれるものが少しずつ抜け落ちていったのは、こうした便利さの積み重ねによるものかもしれない。
記憶の中のディズニーランドには、もっと不完全さがあった。不便だった。だからこそ、そこに人の気配があった。人は案内板の前で立ち止まり、マップをくるくると回して向きを合わせ、道に迷い、偶然たどり着いたアトラクションに歓声を上げた。それらは計画された楽しみではなく、道の途中で拾った幸せだった。
帰りの電車でポケットから取り出す、くしゃくしゃになったマップ。その中に、今日という一日が詰まっていた。破れた角の向こうに、ふざけながら歩いた仲間の笑顔が浮かんだ。もうその紙は存在しない。ただ、スマホの履歴に数字が残るだけだ。ルートも、待ち時間も、すべて記録され、保存され、やがて消されていく。
それでも否定はできない。この変化もまた、時代が求めたものだった。人々は効率を愛し、快適さを選んだ。夢の国もまた、その声に応えたのだ。責めるべきことではない。けれど、ほんの少しだけ、過去に手を伸ばしてみたくなった。
たとえば、誰も見ていないところで、昔の紙のマップを配ってくれていたらどうだろう。使わなくてもいい。ただ、手に持つだけで、胸の奥が少しあたたかくなる、そんな小さな記憶の欠片として。合理性の外にある「無駄」は、いつだって人の心を救う。
ディズニーランドが変わったのではない。変わったのは、時代であり、そして自分自身だったのかもしれない。あの頃の私は、ほんの少しの不自由を、冒険と呼んでいた。
夢の国は今も、そこにある。ただ、夢の形が少しだけ変わった。それだけのことなのだ。
たっくす
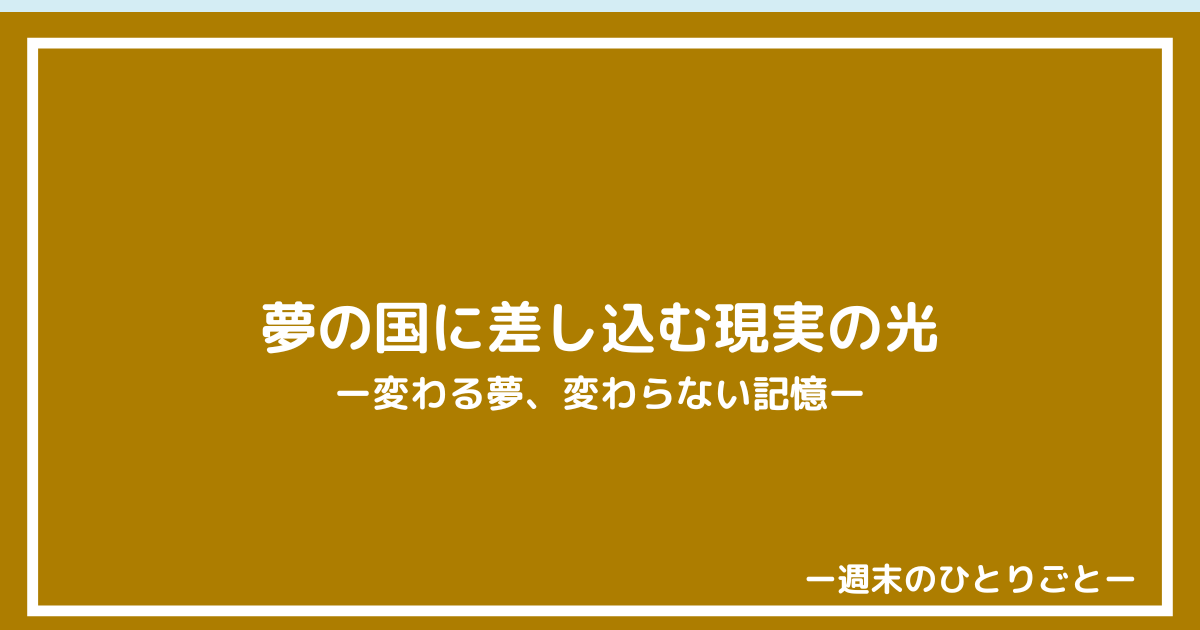
コメント