ポストに届いていた封筒を何気なく手に取った瞬間、どこか遠い記憶の手触りがした。送り主は、卒業してからもう随分と経つ高校だった。表面の印字は滲みもなく、整った字体が無機質に並んでいる。中を開けてみると、今年度の取り組みを紹介するリーフレットと、寄付金のお願いが添えられていた。これまでにも何度か受け取ったことのある類の手紙だったが、今回は妙に胸に引っかかるものがあった。
封筒を読み終えても、財布に手が伸びることはなかった。特に理由があるわけでもない。ただ、寄付をしようという気にはならなかったのだ。それでも、手紙をきっかけに、ふと学生時代の記憶が静かに蘇った。
高校生活は、自分なりに充実していたと思う。派手でもなければ、目立つタイプでもなかった。けれど、放課後の部室、教室の隅、廊下の片隅——どこにいても笑い合える仲間がいた。大声でふざけたり、小さな将来を真剣に語り合ったり。そんな日々が、確かにあった。
だが、今でも連絡を取り合っている友人は、片手で数えられるほどしかいない。多く見積もっても十人には満たないだろう。当時、「一生の友達だ」と信じて疑わなかった彼らとの関係は、時間とともに少しずつ薄れ、今ではほとんど途絶えてしまった。理由は明確には思い出せない。生活の変化、忙しさ、あるいはただの怠惰。きっかけが何であれ、一度離れた関係をもう一度結び直すのは、思っているよりも難しい。
不思議なもので、クラスメイトの中には、さして親しかったわけでもないのに卒業後に偶然再会し、今ではたまに飲みに行くような関係になった者もいる。逆に、当時はほとんど毎日一緒にいたはずの友人と、今はまったく連絡を取っていないということもある。人間関係とは、本当に不確かなものだと思う。一度切れた縁が、思わぬタイミングでまた繋がったり、ずっと続いていたはずの関係が、ある日突然消えてしまったり。そういう不確かさを受け入れるしかないのだと、今は思うようになった。
それに気づくたび、ふと未来のことを考えてしまう。今、日常的に連絡を取っている友人たち——果たして数年後、あるいは十年後、どれだけの人がそばに残っているだろうか。おそらく、その大半はいなくなっている。そう想像するだけで、少し胸がすくような、少し寂しいような感情が入り混じる。
けれど、その寂しさもまた現実の一部なのだと思う。どれだけ時間を共に過ごしたか、どれだけ深い話をしたかに関係なく、人は変わり、環境が変わり、やがては別々の道を歩いていく。どんなに深い絆で結ばれた関係であっても、それは永遠ではない。すべての出会いは、道の交差点のようなものだ。一瞬、交わり、また別れていく。その儚さを受け入れるしかない。
しかし、だからこそ、その一瞬一瞬を真摯に受け止めたいと思う。刹那の交差であっても、確かに心を動かされた記憶は、今の自分をかたちづくる大事なピースだ。時間に風化されない思い出というのは確かに存在していて、それはそのとき誰かと過ごした日々の濃度が生み出すものだ。
今も付き合いのある友人たちは、そうした記憶の中から自然と選び残された存在だ。彼らとの関係は、単なる偶然の産物ではない。何度も途切れそうになりながら、幾度も繋ぎ直してきた道。忙しい日々の中でも、ふと連絡を取りたくなるような人たち。だからこそ、これからもその繋がりを大切にしていきたいと、改めて思う。
過去の友人たちとの関係が薄れていったことを、誰かのせいにするつもりはない。責める必要も、後悔する必要もない。人は変わるし、環境も変わる。むしろ、その自然な変化を受け入れられるようになった自分の成長を肯定したい。
人間関係の価値は、時間の長さではなく、心の深さにある。どれだけ長く一緒にいたかではなく、どれだけ強く互いに影響を与え合えたか。そう思えるようになったのは、きっと年月を経てきたからこそだ。
今の僕にとって、今なお続く少数の友人との関係は、かけがえのないものだ。彼らと語る時間、笑う時間、黙って過ごす時間。そのどれもが、今という瞬間を確かに照らしてくれる。そして、それはやがて記憶となり、人生を振り返るとき、必ず温もりとともに蘇ってくるだろう。
封筒ひとつ。たったそれだけの出来事が、こうした思考の旅へと僕を導いた。寄付金を送ることはなかった。けれど、あの手紙が僕に与えたものは、確かにあった。かつての自分と、今の自分とを、静かに繋ぎ直すような時間だった。そう思えば、この手紙には十分な価値があったのかもしれない。
これからも、人との繋がりを、丁寧に、しかし執着せずに育てていきたい。刹那の中にこそ、本質が宿るのだと信じながら。
たっくす
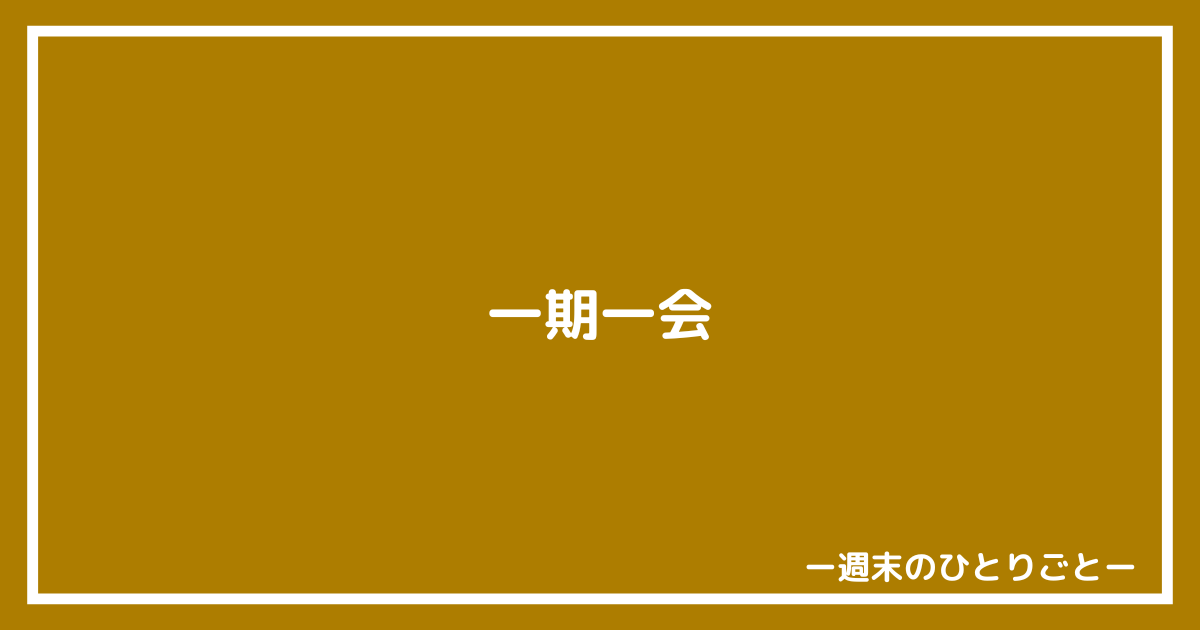
コメント