日曜日の朝、目覚めると、どこかしら心の奥底に黒い雲が漂っているような感覚がある。重たい、けれどもそれが何かと問われればはっきりとした答えが見つからない。日曜日は、なぜこんなにも憂鬱なのか。何が僕をこの感情に駆り立てているのか。しばらく考えてみる。
まず最初に思い浮かぶのは、仕事が始まるからだ。月曜日からはまた一週間が始まり、ルーティンの中に戻っていく。その事実が、日曜日の静けさに影を落としているのだろうか。しかし、ここで一度立ち止まって考えてみる。僕は本当に仕事が嫌いなのだろうか。答えは「ノー」だ。嫌いというわけではない。もちろん、友人と遊ぶことや自由な時間が与えられたら、それを選ぶのは間違いない。しかし、単に「仕事が嫌だから」という理由だけでこの憂鬱を説明するのは、どうにも腑に落ちない。
では、仕事以外に何か原因があるのかもしれないと考え始める。そこに辿り着くのは、週末そのものが終わってしまうことへの抵抗感だ。週末が持つ特別な解放感、日常の枠を外れて自分のペースで時間を過ごせるあの感覚。それが終わる瞬間、まるで風船が破裂するように消え去る虚しさが、僕の中に憂鬱をもたらしているのではないか。
思い返せば、僕はいつも何かが終わることに対して、強い虚無感を覚えてきた。学生時代の文化祭でもそうだった。準備期間が最も楽しく、文化祭そのものが始まると、どこか燃え尽きたような気分になっていた。旅行に行くときも同じだ。旅行先に着くまでの期待感、非日常の世界が広がるであろう予感に胸を躍らせる。しかし、目的地に到着した瞬間、その興奮は一気に落ち着いてしまう。
つまり、僕が憂鬱を感じるのは、仕事が嫌いだからではなく、終わりそのものが持つ儚さ、そしてそれに対する僕自身の反応なのだろう。終わりを迎えるたびに、僕の心にはぽっかりと穴が空き、その空虚さが日曜日の憂鬱を増幅させているのだと気づく。
もし、一生終わらない週末があったらどうだろうと想像してみる。週末が永遠に続けば、この憂鬱も解消されるのかもしれない。しかし、現実にはそんなことはありえない。永遠の週末を迎えるためには、ニートになるか億万長者になるしかない。億万長者になる可能性は限りなく低い。ではニートになるという選択肢が残るが、それはそれで新たな憂鬱を生むことになるのだろう。社会から切り離され、自分の存在意義を見失うような日々。結局、どちらに転んでも、憂鬱からは逃れられないのかもしれない。
憂鬱という感情は、僕たちの人生の中で常に背後に潜んでいるようなものだ。だからこそ、この感情とうまく付き合いながら生きていくしかないのだろう。日曜日の憂鬱も、その一部として受け入れるべきなのかもしれない。終わりがあるからこそ、始まりの輝きが際立つのだ。週末が儚く消え去ることで、次の週の始まりにもまた新しい期待が生まれる。
こうして文字に起こしてみると、少しだけ心が軽くなったように感じる。憂鬱な気持ちを抱えたまま生きていくことも、決して悪いことではないのかもしれない。日曜日の夜、または月曜日の朝、その憂鬱がやってくるたびに、僕はそれを感じ取るだろう。しかし、それは僕の人生の一部であり、受け入れることで少しずつ前に進むことができる気がしてきた。
ありがとう、Blog
たっくす
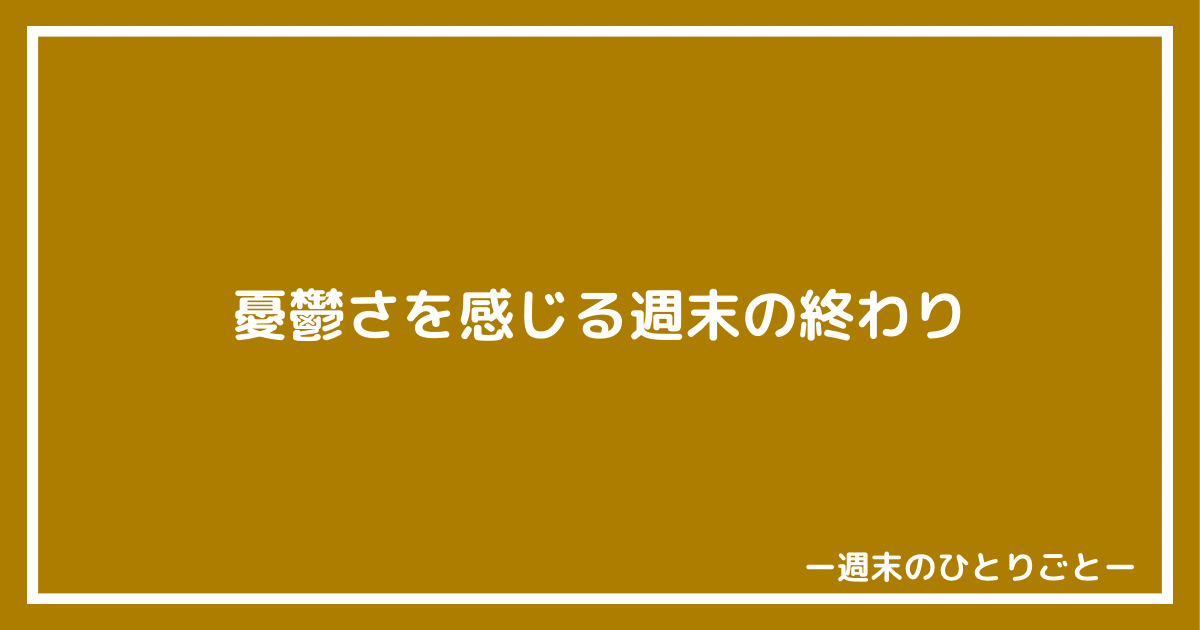
コメント